『民族という虚構』小坂井敏晶 (著)
書評
執筆責任者:Takuma Kogawa
人間どうしは何かにつけて差を見出そうとしていないか。キング牧師の有名なスピーチの背景に横たわっている黒人差別をはじめ、肌の色による区別、民族や国家に対する差別用語など、差に関する言葉や問題は無数に存在する。人種や民族のちがいが差別や戦争の遠因になると思われるが、そもそも人種や民族とは何か、と問われると辞書的な意味以外ではうまく答えられない。本書は人種や民族は虚構により成り立っているものだと主張する。たとえばりんごを分類するとき、色や酸味等のひとつの評価軸であれば簡単に分類できる。しかし、傷の有無や香り等の複数の要素を同時に評価して分類しようとすると、とたんに分類できなくなる。これを解決するには、恣意的にちがいに重みづけをするしかない。人間の場合は、たまたま肌の色が現在の「人種」という分類をするのに採用されただけであり、髪の色や血液型、身長を重みのある指標と考えれば現在とは異なる「人種」が生まれていた。民族は、辞書的には文化的背景をもとにした分類である。人種での説明と同様に、文化の重みづけによって民族の境界は異なってくるだろう。現代は言語や宗教が民族の境界を定める要因であると考えられるが、要因は不変ではない。国内で言語や宗教が異なる「民族」が複数あったとしても、その国が戦争をしかけられたときはその「民族」の境界は一時的に融和するだろう。外部の敵の存在により、相対的に国内の言語や宗教の差が気にならなくなるからだ。歴史的には、ユダヤ人移民によって建国されたイスラエルは、ヒトラーによるユダヤ人弾圧という「外」の要因が彼ら集団の同一性を意識させたことが建国に一役買ったと考えられる。先に人種や民族といった差があり、同一人種・同一民族が集まって国境ができるのではない。先に政治や経済をめぐって差や対立があり、対立運動が境界を作り、その内側が人種や民族として表象されるのである。
(793文字)
追加記事 -note-






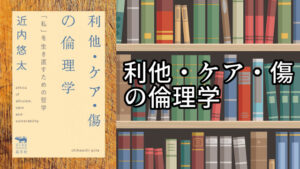





コメント