『つかふ』鷲田清一(著)
書評
執筆責任者:ingen
本書のタイトルは「つかふ」である。副題には「使用論ノート」とある。人を使う、人に仕う、道具を使う、道具に使われる。これらのことは全て本書で扱われるテーマだ。「つかふ」というタイトルについて著者は次のように書いている。「「使う」「使われる」広やかな意味を持つ「つかふ」をもういちどわたしたちの暮らしにたぐり寄せる」。その言葉通り本書には道具を使うプロである伝統工芸の職人、体を使うプロである武道家、人を使う例とし介護の現場の話などさまざまな「使う」を生業にする人その他さまざまな人々の言葉が引かれる。著者がはじめにの章で書くのは人を使うと言うことだ。人を使うと言えば搾取という言葉が一番に浮かんでくるという人も多いだろう。一方で他人との深い信頼の中で体を使い合うと言う場面もある。人は助け合って生活している。その共同生活の中には人は「ちょっとごめん」と言って、傍の他人をよく道具として使う。それなのに何かを使うとりわけ人を使うと言う場面になると現代人の物言いはなぜかとても窮屈なものになる。それは著者によると「使う」ということが「所有」と言う観念と結びつくことによって起こるという。所有について本文を引くと「西欧近代の所有権をめぐる議論のなかでは「自由処分権」、つまりある物を意のままにしてよいという権利と結びつけて考えられてきたと言うことである。」とある。どこまでが私が意のままにしてよい領域で、どこからが他人の領域なのかと言う境界の意識がここから現れてくる。「使う者と使われる者の間に「べし/べからず」と言う規範的な意識が挟まるのである」。この意識が「使う」と言う言葉を窮屈なものにする。本書ではその意識をリハビリするような使う使われるの関係性についての話が多く出てくる。気になった方は読んでみてほしい。(753文字)
追加記事 -note-






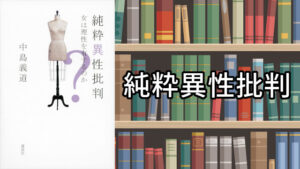


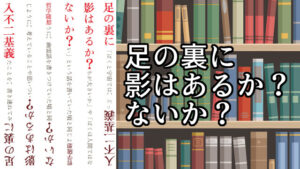


コメント