『読んでいない本について堂々と語る方法』ピエール バイヤール (著), Pierre Bayard (原名), 大浦 康介 (翻訳)
書評
執筆責任者:Yuta
本をたくさん読んでいる人が教養人で、本を読んでいない人は教養人ではない。古今東西の社会に暗に存在する共通認識である。しかし、果たして本当に本をたくさん読んでいるのがいついかなる時も称賛されるべき良いことなのか。本を読んでいない人はその本についてコメントしてはいけないのか。そもそも教養とは何か。良い本の批評とは何か。そのような疑問を深堀して考えていくのが本書の内容である。『読んだことのない本について堂々と語る方法』というタイトルに騙されてはいけない。これは単なるハウツー本ではないのである。最初の章では、未読の段階にもいくつかあり、本をそれらに分類したときに読んだ本のうちに入るかを議論している。次章ではどんな状況でコメントするかに分類して、聴衆と批評家それぞれの置かれた状況を分析し、的確なアドバイスがされている。最後の章はコメントをするときの心がまえについてかかれている。自分自身の考えを本の解釈として押し付けるのは簡単なことで、欠点を見つけやっつけ仕事的に批評する手口や、一見申し分ない本をいかにこき下ろすかについても触れられていて、興味深い。また、書評は作品について語られるより、自己を対象にして書かれている方が良いという話で締めくくられている。そう、読んだことのない本について語ることはある種の創作活動なのである。しかし何といっても、読んだことのない本について堂々と語るために本書を読むさまは何とも滑稽である。本を読み終えてこの書評を書いている僕が、本当に全部読んだのかを確かめるのは不可能である。そもそも本を読んだといえる基準は人それぞれだからである。本の具体的な内容に触れずとも、その本と他の本との関係性、要するにその本の位置づけを知っておきさえすれば、十分その本についてコメントはできるという立場が、この本では取られている。読書を営むすべての人に、一度は読んでみてほしい名著である。
(800文字)
書評
執筆責任者:ゆーろっぷ
あなたが熱心な読書家であればあるほど、「読んでいない本について語る」という行為に言いようのない嫌悪感を覚えるかもしれない。我々は社会生活──多くの場合学校教育──を通じて、書物とは客観的かつ不動の対象であり、好き勝手に語ることの許されないある種の「神域」なのだという共通見解を形成している。この権威付けによって暗黙のうちに規定される規範に背くことは、権威に異議を唱えることと同じであり、自身を社会的な窮地に追い込みうる。そのため、人々は読んでいない本について語ることを避け、「必読書」と呼ばれる本を読んでいないことにやましさを覚えてしまう。しかし筆者は、こうした書物や読書の神聖化に由来する禁忌をあえて犯し、読んでいない本について語ることの意義を強調する。さらには、ある本について語る際には、むしろ非読の方が良い場合もあるという。筆者によれば、そもそも本を「読んだ」「読んでいない」という状態は極めて曖昧なものであり、どのような本も常に非読と完読の中間に位置している。極論を言えば、あなたがこの書評を読んでいる時から、さらには本書のタイトルを目にした瞬間から、「読書」は既に始まっているのである。読書という営為が孕むこうした曖昧さは本書の中で様々な角度から分析されるが、筆者はこの曖昧さを逆手にとって、読書を「想像」及び「創造」の機会と捉えるべきであると主張する。すなわち、(読んでいない)本を媒体として、自己発見のための独自のテクスト空間を生成するということであり、それが「自分自身について語る」という本書の教えでもある。そして、その「創造」は本を「読まない」ことによって初めて可能になるのである。さて、ここで私について言えば、現時点で本書の内容の大半は忘れており、そもそも流し読みしただけで全て読んでいるわけでもない。ということで、読者の方もこの本について「読まずに」語ってみてはいかがだろうか。
(800文字)
追加記事 -note-

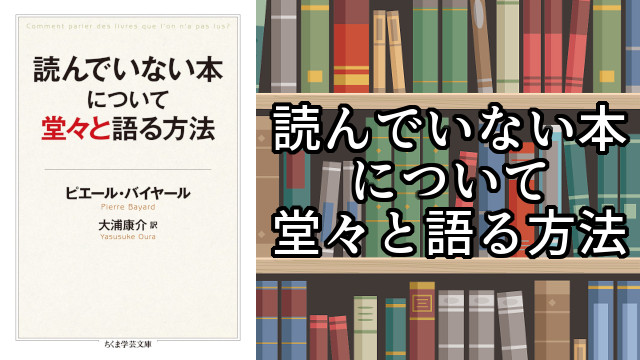










コメント