『人間はどこまで家畜か』熊代 亨 (著)
書評
執筆責任者:ゆーろっぷ
現代の豊かさや徹底された安心安全は過去に前例がないほどである。都市の治安は良く、多くの人が職に就き、衣食住に困ることもない。科学技術の発展はすさまじく、かつて理想とされた社会が実現されている。しかし他方で、そうした社会の恩恵を受けるために必要な能力・資質の基準はますます高まり、その中で多くの人が心を病み、社会生活に困難を覚え、医療や福祉の支援に頼らざるを得ない状態となっている。物質的豊かさがかつてない水準にまで達した一方で、ともすると人間性が疎外されているこの逆説的状況をどう説明すればよいのだろうか。精神科医である熊代氏は本書の議論を通して、生物学的な知見、特に「自己家畜化」という鍵概念と人文科学的知見とを組み合わせ、その背後にある問題の輪郭を浮かび上がらせている。自己家畜化とは、人為的な家畜化を経ることなく、より穏やかで協調的な性質を持つように自らを進化させる生物学の概念で、イヌやネコ、そして人間自身にも起こったとされるが、そのような生物学的進化が追いつけない速さで社会・文化的環境が変化している事実に著者は焦点を当てる。こうした加速社会は、身体の健康・長寿、ポリコレ的「正しさ」などが担保されるという意味で、ある種のユートピアを具現している。しかしその裏側では、我々は自己家畜的振る舞いをソフトガバナンスの形で絶えず要請され、そこから逸脱する者は治療・矯正・隔離の対象となる。従来の暴力装置とは違った新たな権力による管理構造と、進歩という名のイデオロギーの下で、更なる身体性の排除=人間疎外が起こっているのだ。人間の身体的下部構造が抑圧された社会を、養老孟司氏は著書『唯脳論』の中で「脳化社会」と呼んだが、それは現代社会という巨大な現実となって、付随する病理とともに我々の目の前に立ち現れている。本書の一読を通じて、そうした「現実」と人間性の未来について一考してみてはいかがだろうか。
(800文字)
追加記事 -note-

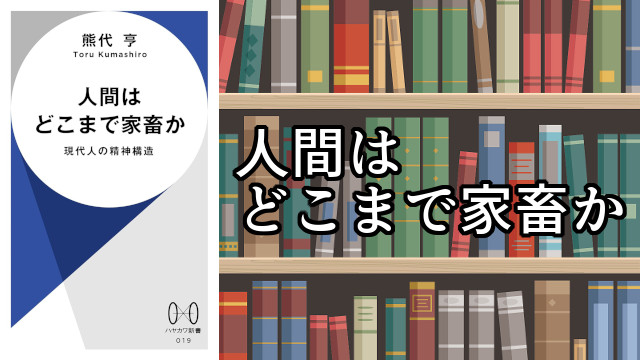
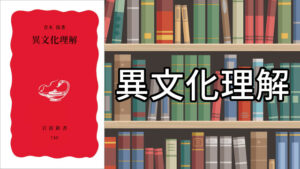
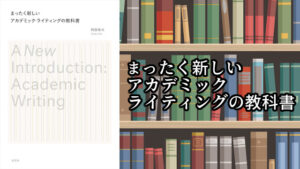
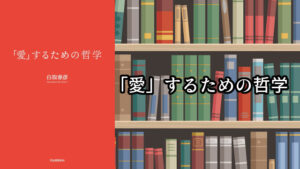
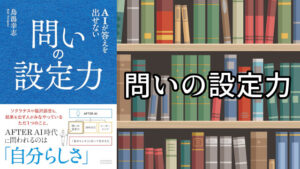
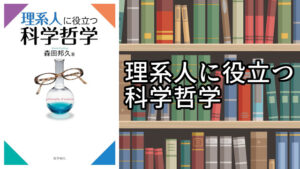
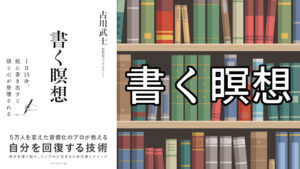
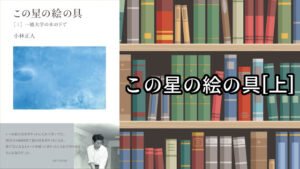
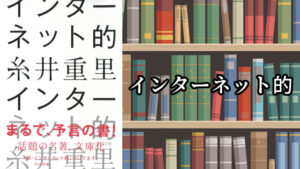
コメント