『永遠も半ばを過ぎて』中島らも(著)
書評
執筆責任者:コバ
言葉。私たちは言葉を用いて日々、他者とコミュニケーションを取っている。会話だろうか、文章でのやり取りだろうか。ツールも様々だろう。対面だろうか、電話だろうか、SNSを用いてだろうか。目的はお喋りだろうか、勉強だろうか、仕事だろうか。本書は写植屋の波多野と詐欺師の相川の2人の主人公が登場する。写植とは写真植字のことだが、与えられた言葉をそのまま印字する写植屋と嘘八百を並び立ててその嘘八百でそのまま人を騙し通してしまう詐欺師。全く真逆の2人のようだが、相川は物語の中でこう語る。「僕の直感だがね。人間の心っていうのは、こういう、イチジクというか、キンチャクというかそういう形をしてる」「このキンチャクの上部の、ひだになって締まってる部分をね、ゆるめてやるんだよ。そこから誰かがはいってきてくれる」そして波多野もまた、客から与えられた文字を印字している。それもまた、文字というものを通して誰かが波多野に入ってきていると考えられるのではないだろうか。そして我々もそうではないだろうか。我々が今このように日常生活で言語を運用することができているのは先人が言語を発明して、それが社会に現在の形で伝播しているからである。先人達から私達まで綿々と言語運用が続いてきたこと、それは先人達が私たちに言葉という形ではいってきていると考えることもできるのではないだろうか。そうであるならば、ここまで読んでいただいた方は考えるかもしれない。この書評を読んでいる時点で私があなたにはいってきてしまうのではないか?と。相川の持論を借りるのであれば、キンチャクのひだの部分を閉じていただければ私はあなたにはいってこれない。もしはいってきてほしくない方は安心して閉じていただきたい。つまり、他者を受け入れられるか否かは「能力」の問題ではなく「やる気」の問題なのだ。そして、私はそれを「勇気」と呼びたい。
(786文字)
追加記事 -note-

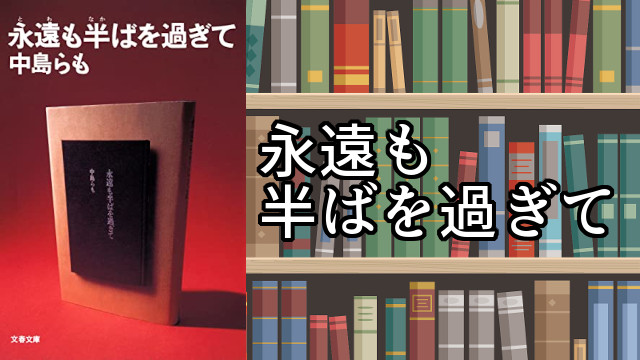







コメント