『教養の書』戸田山 和久 (著)
書評
執筆責任者:けろたん
学び続けることは良いことだ。知らないことを知ることは良いことだ、できないことができるようになることは良いことだ、と素朴に思う。しばしばこの程度の意味で「教養」という言葉が用いられる。ほんとうに教養とはそれだけなのだろうか。自分が何かを知り、わかるようになることに、単に「良いこと」以上の意味を求めたくはないだろうか。そのためには、教養とはどういうものか、掘り下げなけばならない。教養がなぜ必要なのか、捉えなければならない。教養をどうやって身につけるのか、知って実践しなければならない。本書はその手引となる一冊である。教養とは、生物としてのヒトについてのものであり、社会に生きる人間としてのものでもある。避けるべき・止めるべきことについての「べからず」集であり、やるべきこと・望ましいことについての指針でもある。言葉ついてのものであり、振る舞いについてのものでもある。自分がどうするかということであり、人とどう関わるかということでもある。自身を批判的に捉えるためのものでもあり、他者を信頼して任せるためのものでもある。「XXを知らないやつは教養がない」というように、ともすれば自分が常識だと思っているものを持ちあわせない他者を軽蔑する含みをもつのが教養という言葉だ。そのような格付けのために持ち出される教養が放つはなもちならなさを本書は感じさせない。著者の専門である科学哲学、それと関連の深い分野である論理学、認知科学の知見の一つ一つが、現代において考えることを考えるための、基礎ともいえるような知識だからだろう。著者が文学や映画のさりげない描写からメッセージを汲み出すそのしかたがまさしく教養によって深められた読解、鑑賞だと実感できるからだろう。現代において知識の基盤となりうる知識そのものをもちいて、知識の共通基盤の重要性とそれを支える精神性を説く一冊。
(778文字)
追加記事 -note-


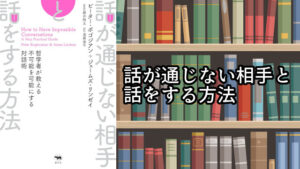





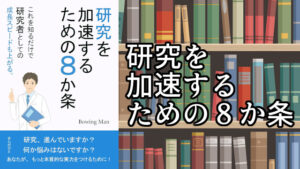

コメント